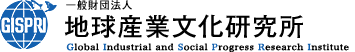昨年10月13日(木)から15日(土)にかけて、パシフィコ横浜で「GLENTEX'94」が開催され、同時に当研究所主催の標記タイトルのセミナーが開かれた。今回は本セミナーの講演要旨を紹介する。
「企業経営と環境問題」
通商産業省環境立地局地球環境対策室室長
内山俊一氏
(本件については、本誌1994年12月号に掲載された「地球環境問題懇談会」の内容と一部重複するため、重複せず、また、重要なテーマである「貿易と環境」の部分のみ記す)
貿易と環境というテーマはウルグアイラウンドの後の貿易問題として非常に重要である。問題の所在は、従来のGATTルールの基本的命題である貿易の自由化が環境に悪影響を及ぼす場合と、逆に環境保護目的の貿易制限措置が自由貿易に対して歪曲効果 を持つ場合の2つの問題がある。いわゆる、貿易政策と環境政策の両立をいかに図っていくかがこの問題の所在である。
現行のGATT規定は、自国の環境保全を目的とする措置だけを対象とし、自国の管轄権の及ばない環境問題や地球全体の環境保護を目的とした貿易措置は対象としていない。しかし、気候変動、オゾン層、森林といった地球共通 の財産の保護のためにはある程度の貿易制限措置が必要な場合があることが国際的コンセンサスとして認識されており、すでに国際環境条約の中には、一定の貿易制限措置が盛り込まれているものがある。
これに対する各国の立場は、まず、米国は、貿易と環境の問題には非常に積極的である。特に、発展途上国の環境保護への取り組みを強化させるためには、一方的な貿易制限措置が必要であり、一定の基準を満たせば貿易制限措置の発動を認めるべきであると主張している。例えば、グリーン301条といったアイデアが議会でも取り沙汰されている。しかし、これらの議論は発展途上国との競争に直面 している産業界が偽装された保護主義の口実に用いる恐れがある。一方、欧州でも貿易と環境の新たなルール作りには前向きであるが、米国が主張しているように、自国の管轄外の環境保護のために一方的な貿易制限措置を行うということに対しては、非常に消極的であり、逆に、これまでのGATT体制である多角的貿易体制の根幹を揺るがす問題であるとする認識を持っている。
日本は、国の環境政策はその国の主権の問題であり、一方的な貿易制限措置ではなく、資金や技術の提供により、その国が環境配慮を積極的に行えるような環境作りを基本にしている。日本は産業公害の克服と高い経済水準の維持を両立してきた経験を持つ国として、環境関連技術を積極的に発展途上国に移転していくことが重要であると認識している。地球環境問題の特質を考慮して、国際的な制度的枠組み作りに積極的に貢献していきたい。
「温暖化防止のための技術的対応と企業の役割」
東京農工大学工学部教授 柏木孝夫氏
国でも企業でも環境にネガティブな姿勢を示したら、これを克服するためには多大な努力とコストを要する。特に、事後のコストは事前のコストに比べて約10倍高いと言われている。よって、環境を上位 に位置付け、それから経営理念を構築するべきである。地球規模の環境問題はこのことを我々に教えてくれた。
エネルギーについてはカスケード利用を進めるべきである。水力発電ではカスケード利用が行われている。山の上の方に発電所を作り、その下流で再び水が集まった所があればさらに発電所を作る。このように山の上の方から徐々に何回でも位 置エネルギーを電力に変えていく。しかし、熱のカスケードはそうはいかない。例えば、ガスの燃焼は1,600・C位 になるが、これで70~80。Cのお湯を沸かすのはもったいない。例えば、まず、熱を製鉄工場で使い、排熱を各種乾燥工場や食品工場で使い、最後に暖房に使っていく。これが熱のカスケーディングである。これを産業や民生の従来のエネルギーフローの中でどうやって構築していくかが課題である。
しかし、熱のカスケードではすぐ近くに次の利用施設が現状ではあまりなく、熱は遠くまで運ぶことができない。よって、電気のビジョンは避けて通 れない。すると、高温での利用がなくて、低温の民生需要だけだとすると、高温の燃焼熱を使用したら、内燃機関や燃料電池などで電気を取り出し、低温の排熱を民生に利用する熱と電気のカスケード、いわゆるコージェネレーションとなる。わが国は、温暖化防止のためには、さらなる省エネルギーが必要であり、その骨子はカスケード利用であろう。これには、熱のカスケードもあれば電気と熱のカスケードもある。
2050年を見通 した環境調和型エネルギー技術を列挙すると、まず、核分裂・核融合の原子力が挙げられる。核分裂は2040~50年に商業化される核融合への橋渡し役と考える。ソーラー、水素、クリーン化された石炭(液化、ガス化)、小型民生用燃料電池(固体電解質型は2015年頃)は2010年頃に実用化されるだろう。宇宙太陽電池は長期的には温暖化防止対応技術の一つとなろうが、2040~50年が実用化の目途である。100万kW程度のパネルを宇宙空間に打ち上げ、マイクロウエーブで地上に電力を送る。そして砂漠や海上などに2km2程度の受け皿を作り、電力を受ける。目に見えないマイクロウエーブをどうチェックするのかが問題であるし、武器への転用の恐れもある。超伝導技術は電力の負荷平準化問題の解決策である。今の揚水発電の効率が70%、一方、超伝導で一旦余っている夜間電力を貯蔵できれば、90%の効率が可能と言われている。実用化は2040~50年であろう。CO2回収処理は2010年、放射能廃棄物対策は2030~40年の実用化が予想される。水素利用国際エネルギーネットワーク(WE-NET)は、海外の再生可能エネルギーで電力を作り、この電力を使って水を電気分解して水素を作り、この水素をメタノールやアンモニアなどに変換して船で日本に運び、日本でその逆反応を起こして電力と熱を得るというシステムである。再生可能エネルギーを国際的に有効に使うためには、需要と供給の場所が離れていることが多いため、このような構想が必要となろう。
1994年6月「長期エネルギー需給見通
し」の改訂が行われ、再生可能エネルギーなど新しいエネルギー源の供給目標が追加された。この中でゴミ発電の目標も入っているが、今後のゴミのビジョンが必要である。我々はゴミをバイオマス燃料と捉え、ゴミ発電によって日本の基幹一次エネルギー源にしたいと考えている。大きな焼却炉でないと効率が悪いため、小さなゴミ焼却炉ではゴミを燃やさないで圧縮し、生石灰や消石灰などを加えてペレット状の固体燃料を作る工場とし、大型の発電設備を有する焼却炉に運んで燃やす。これがゴミのこれからの生き方ではないか。
「環境管理・監査の標準化の動向」
産業環境管理協会 常務理事 中山哲男氏
環境管理の規格化については、ISO(国際標準化機構)のTC(Technical Committee)207で行われており、参加国は現在30か国を越えている。TC207には6つのSC(Sud Committee)があり、SC1環境管理システム、SC2環境監査、SC3環境ラベル、SC4環境パフォーマンス評価、SC5ライフサイクルアセスメント(LCA)、SC6用語・定義である。その下にワーキンググループ(WG)があり、ワーキングドラフト(WD)を作成するための作業を行っている。日本でも、規格審議委員会(委員長は東大の茅教授)を設置し、日本の対応を検討し、各WGに専門家を派遣して、外国との折衝に当たっている。WDが作成されると、コミッティドラフト(CD)として参加メンバー国のレビューを受け、承認が得られれば国際規格案(DIS:Draft International Standard)となり、ISO加盟国の投票を経て国際規格となる。
SC1の環境管理システムの構成は、環境方針、環境計画、適用及び運用、チェック及び是正措置、経営レビューなどから成る。環境方針では、経営者は企業活動や製品サービスの環境への影響を勘案して環境指針を作成し、全ての従業員に適用し、一般 にも公開する。環境計画では、企業は企業活動、製品、サービスが環境に影響を及ぼしたり、その可能性を見極める方法を確立し、目的と目標を文書化する。適用及び運用では、企業における環境問題の最高責任者は他の職責と無関係に任命され、環境に影響を及ぼす業務に従事している従業員は十分な教育を受けなければならない。環境計画達成度のチェックと是正については、環境計画に書かれた目標などを定期的に評価し、未達の場合には原因を究明し、是正措置をとる。経営レビューについては、経営者は環境管理システムが有効であることを保証するため、定期的にシステムの検証を実施しなければならない。すなわち、環境方針をたて、計画し、運用・適用し、チェック・是正して、レビューする。そしてその反省から、再び環境方針をたてるというサイクルで環境に対する企業行動をグレードアップしていくシステムを構築していくことが、環境管理システムである。
SC2の環境監査関係では、一般 原則、環境管理システムの監査、法的適用性の監査、パフォーマンスの監査、サイトの監査、環境声明書の監査、環境監査人の資格要因、環境監査プログラムの管理、初期環境監査レビュー、環境アセスメントの10項目が討論されている。一般 原則、環境管理システムの監査、環境監査人の資格要因の3つが優先されており、1996年4月から9月にかけてISOとして成立すると言われている。環境アセスメントについてはやらないことになった。
その他のSCは、ゆっくりした速度で進んでいる。
SC3の環境ラベルについては、世界各国でバラバラに進んでいるラベルについて最低限の基準作りをWG1で行っており、WDが作成されたところである。WG2は重要で、例えば、リサイクルや省エネなど企業が環境に対して行った取り組みについて、自己主張する際の基準、用語、定義の取り決めを行っており、CDがまとまった。WG3の基本原則については、米国が主張したため、環境ラベルとは何かなど基本的な事柄についてWDをまとめているところである。
SC4の環境パフォーマンス評価については、この概念がわかりにくく、SC1との関連もあり、原則論の議論が多かった。人の関わるシステムと関わらないシステム(オペレーショナルシステム)とそれを取り巻く環境の3つに分けて、それぞれについて検討しているところである。
SC5のLCAについては、WG1~ WG5まであるが、LCAがそもそも規格になるのかどうかの議論がある。実際には、実施要領ということで、LCA全体の枠組みをWG2(インベントリー)、WG4(影響評価)、WG5(改善評価)で大まかな原則を出したところである。
「環境リスクと企業経営」
東京海上火災保険(株)
企業リスクコンサルティング室課長 吉田通之氏
環境と経済は一つである。経済活動により環境が汚染され、環境が破壊されると経済は成り立たない。環境に対して企業は二面 性を持っている。企業は環境を汚すし、汚染された環境をきれいにすることもできる。ここに、環境問題は企業にリスクとチャンスを提供する。企業にとって環境問題はコスト増だけをもたらすという考えは近視眼的である。環境をきれいにする技術を持つ企業にとっては、この技術がビジネスチャンスを生む。廃プラスチックからポリエステル繊維を作ったり、牛や馬の糞から有機肥料、発泡スチロールから重油、ゴミ焼却熱を利用した発電などいろいろな環境ビジネスや環境技術が出てきている。これらは、決して大企業だけから生まれているわけではなく、あらゆる企業に可能性がある。
企業は、海外の動きに注目しておく必要がある。環境規制や法制については、米国にはスーパーファンド法という土壌汚染を取り締まる非常に厳しい法律がある。ドイツには包装廃棄物に関する法律があり、あらゆる包装物の80%をリサイクルしなければならない。欧米では、製品が廃棄物になったらできるだけ解体しやすいように設計するDFD(Design For Disassemble)の思想がある。例えば、欧米のDFDの設計思想で作られた電気洗濯機は約15分で解体できるが、日本の製品は約1時間かかると言われている。
企業にとっての環境リスクには2つある。一つは法律上のリスクである。法律違反により、罰金、責任者の逮捕、操業停止、追加の設備投資などが発生する。もう一つは企業イメージに対するリスクである。環境保護団体の声を無視できなくなっている。欧米では「緑の消費者」が大きくなりつつある。また、NIMBY(Not In My Back Yard)といわれる自分の近所に汚染源があることを嫌う人々がいる。さらに、社会的責任投資と呼ばれる考えがあり、企業に投資する場合、単に企業の業績だけでなく、企業が環境や雇用、人種問題などに対して社会的責任をとっているかどうかを判断材料とするものである。米国では、株や債権への投資の約10%が社会的責任投資のものさしで判断されている。ここには企業は誰のものかという議論がある。法律上は株主に所有権があるが、経営者、従業員、消費者、地域住民など企業に利害関係を持つ全ての者のものという考えがある。よって、企業は利潤を出して株主に高い配当を出すだけでなく、これら全ての人々の福祉を向上する必要がある。この点からも企業は環境問題を考えていかなければなりらない。
環境管理・監査についても国際的動向に注目しておく必要がある。1995年4月に施行予定の欧州の環境管理・監査規格(EMAS)は自主的なものだが、この規格をとらないと欧州に輸出できない可能性がある。しかもこの規格をとるためには、一説によると、数千万円から1億円位 、期間も1~2年かかると言われている。それに対して今から環境管理・監査については十分準備をし、あらゆる企業活動においてできるだけ環境への負荷低減の努力をしておく必要がある。
「企業は世界の中で良き企業市民となることを旨とし、環境問題への取り組みが自らの活動と存在に必須の要件である。」(経団連『地球環境憲章』より)。これからの企業は良い製品を安く提供することだけではなく、「accountability」が必要となってくる。これには、説明できることと責任がとれることの2つの意味がある。自らの企業活動や製品が環境にどのような負荷や影響を考えているのかを世間に説明できること、また、環境に被害が出た場合に損害賠償の責任はもちろん、環境への負荷を改善していく責任もとれることが必要であり、これができる企業が21世紀に生き残れるだろう。